「狐の嫁入り」の由来とは?
皆さんは「狐の嫁入り」って聞いたことがありますか?
Wikipediaによると、狐の嫁入り(きつねのよめいり)は、本州や四国・九州に伝わる怪異のことです。
その現象には大きく分けて、提灯の群れを思わせる夜間の無数の怪火と、日が照っているのに雨が降る俗にいう天気雨の、2つのタイプがあります。
いずれの現象も、人間を化かすといわれた狐と関連づけられるほか、古典の階段や随筆、伝説などには異様な嫁入り行列の伝承も見られるということです。Wikipediaはこちら
ではどうして天気雨のことを「狐の嫁入り」というようになったのでしょうか?ちょっと調べてみましょう。

なぜ晴れているのに雨が降るのか?
ウェザーニュースによると、天気雨が生じる理由は、主に3つだそうです。
- 雨を降らせた雲が消えてしまった場合(雲の中で作られた雨が地上に落ちるまでには10分以上時間がかかりることがあるため)
- 雨を降らせた雲が小さかった場合(晴れている頭上に雲がなくとも、離れたところに目立たない、小さな雨雲が存在することがあるため)
- 雨が流されてきた場合(離れた雲の中で作られた雨が強風に流されて、太陽が出ている場所で地上に落ちてきたため)

なるほど、だから雨が降っていても空は晴れていることがあるのね
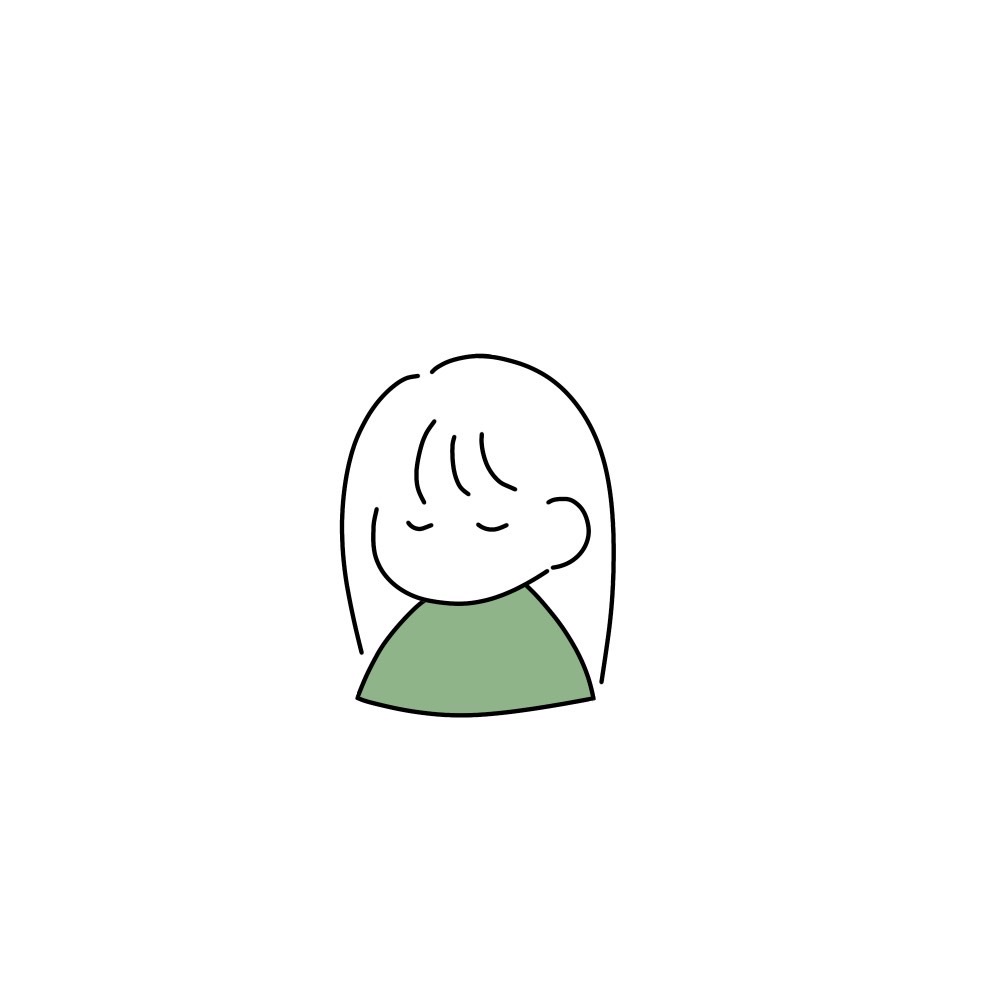
じゃあなんで「狐の嫁入り」っていうのかな?
なぜ「狐の嫁入り」という呼び名がついたのか?
【きつね‐の‐よめいり狐の嫁入り】
1.日が照っているのに、急に雨がぱらつくこと。日照り雨。
2.夜、山野で狐火が連なって、嫁入り行列の提灯(ちょうちん)のように見えるもの。
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)

狐の嫁入りという言葉は、無数の狐火が提灯行列のように連なって見える現象の俗称を指す場合もあります。
「狐火」とは、発生源が不明な火のことであり、火が狐の口から吐き出されたものとして表現されている言葉です。
別名として「鬼火」「幽霊火」「陰火」などとも呼称されます。
列をなして灯るおびただしい数の怪火は、人ならざる者の火であり、怪火の大群は嫁入りなどの祝賀を表す提灯行列だろうという見立てをもとにした表現のようです。
夜間、野原や山間部などで多く見られるといわれています。
ほかにどんな呼び名があるのか?
冒頭で、「狐の嫁入り」は「本州や四国・九州に伝わる怪異」だと述べましたが、それ以外にどんな呼び名が存在するのでしょうか?
北海道を除くほとんどの地域では「狐の嫁入り」と呼ばれていますが、調べてみるとほかにこんな名称が存在することが分かりました。
「狐の嫁入り」以外の名称
| 名称 | 地域① | 地域② | 地域③ |
|---|---|---|---|
| 狐の嫁取り | 青森県南部地方 | 埼玉県草加市 | 石川県鳳至郡能都町 |
| 狐雨 | 神奈川県茅ケ崎市 | 徳島県麻植郡 | |
| 狐の嫁取り雨 | 千葉県東夷隅郡 | ||
| 狐の祝言 | 静岡県沼津市 |
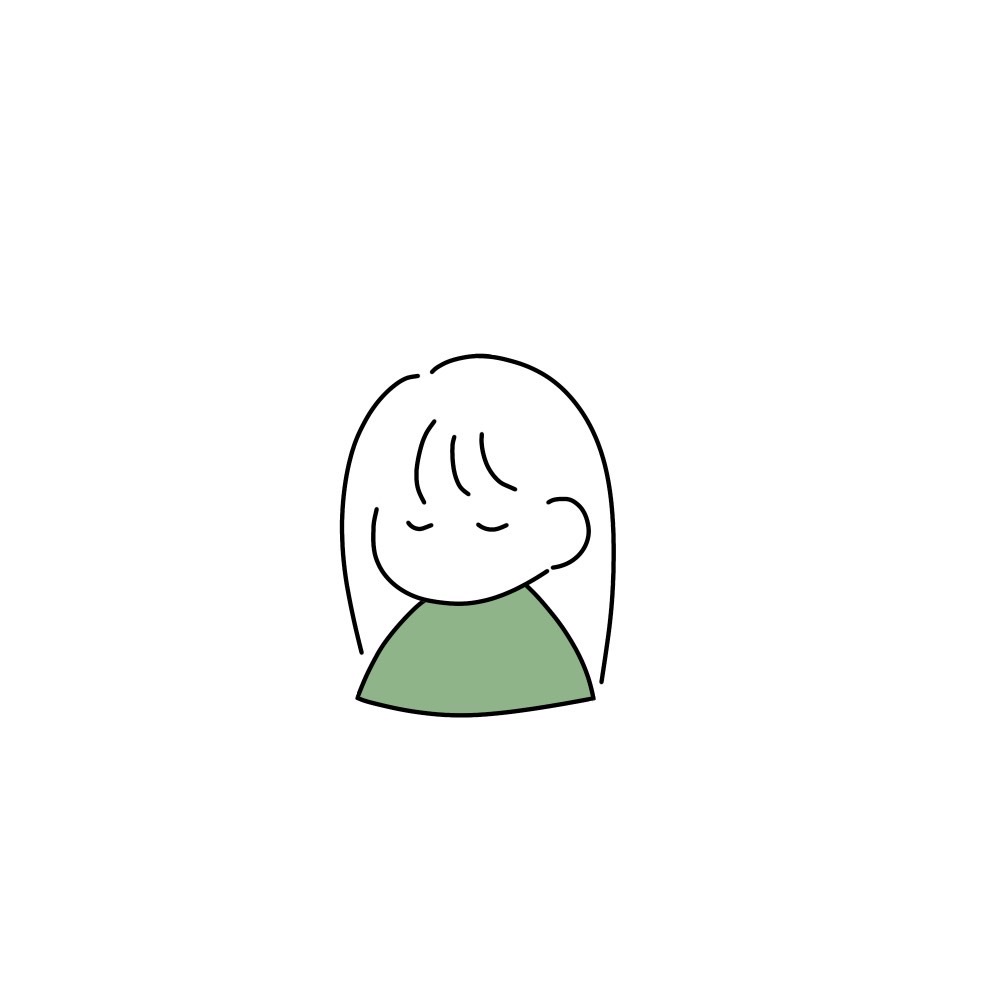
じゃあ北海道では天気雨のことをなんと呼んでいるのかな?

「蝦夷雨」と言うそうだよ!
まとめ
いかがでしたか?
自然現象にはさまざまなものがありますが、まだ物事を科学的に捉えることがなかった時代に、先人が名付けた「狐の嫁入り」という名称には、なにか親しみのようなものが感じられるのは私だけでしょうか。
ちなみに英語では何というのか、気になって調べてみました。
すると、「sunshower」ということで、日本の「天気雨」と同じ感覚なんですね。
でもアメリカ南部では、The devil is beating his wife. というスラング表現が使われることもあるそうなんです。
これは、「悪魔が妻を殴っている」という意味で、晴天時の雨を比喩的に表現したものです。
ちょっと怖いですね💦
ぜに皆さんも、天気を表すいろいろな名称を探してみてください!
癒庵



コメント